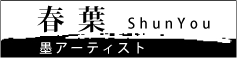塾長の教育相談
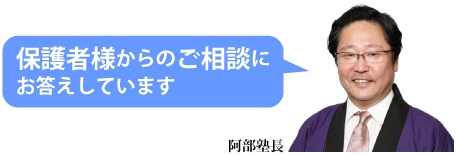
2018/06/10
コーチングの基本は何ですか?子供に接するときに使えるものでしょうか?
コーチングにもいろいろな考えがありますしいろいろな組織もございます。今回は(社)スクールコーチング教会のコーチングをお教えします。私たちは依存するスタイルから自立して社会に生きる青少年を育てることをモットーにしています。
コーチングの基本は「傾聴」についてお話をします。
まずはしっかりと相手の話を聞くことから始まります。
その際には相手の話に集中して相槌を打ちながら相手が話しやすい形にします。
その時、自分はこう思うからこうだという自分の意見を言わずにただただ聞ききることに集中してみてください。
親子間ではどうしても感情が入りやすくなりますから、途中で口を挟まないことに注意してください。
「答えは自分の中にある」
話をすると話しながらああこうだなと自分で気づきが生まれます。
話すことは問題を放すことにもつながります。
その際「ああそうなんだ、それで」という言葉を入れながら相手が話を続けて安くしてあげてください。
その際、相手が沈黙したら、沈黙に付き合ってください。
問題解決を無理にしようとせずに話を聞くことにまずは専念してみてください。
話をしてスッキリした気分になることも大切なことなのです。
まずは相手が話をしたそうだなあと感じた時に「話を聴くぞ」というスイッチを入れて聴いてあげてください。
2018/05/17
2020年の新テスト対策記述問題対策はどうすればいいですか
数学、国語に記述が入ってきます。英語は4技能、読む、聞く、書くことに加えて「話す」は入ってきます。国語は文章を書く習慣を意図的にしなければかけるようになりません。
言いたいことをまとめる。要約の字必要性が増してきます。
小学生ならまず主語、述語を意識して文章を読み、それを抜き出すことから始めましょう。
1行要約からですね。
その次に書き方です。起承転結を意識すること。
小論文なら筆者の言いたいことを抜き出して文章をつなぎ、さらに言いたいことを絞る。
そこから自分の意見を添える。中高一貫対策クラスでは小論文指導を行っています。
これは小中高校生においても文章の難易度の違いはあってもその方法は同じです。
まずは言いたいことを抜き出しまとめること、つまり要約の練習が必要です。
もちろん文章を書くにあたっての漢字、知識は読書をするなど身に着けておかねばなりません。
高校時代もそうですが「いかに生きるのか」というテーマをもって生きざまを問うものを読んでいくことがお勧めです。
そうして自分でどうするのかを考えてみることが大切です。
単に言われたことをするのでは、上辺だけの学習になってしまいます。
その根底にある本質の部分を考え見抜く力を高校時代に養い大学で何を学び将来どうしたらよいかを考えるべきなのです。
そういった本物志向がある者の文章とそうでない者の違いは大きいといえます。
まずは本物志向、「どういきるのか」を考えるように資することが大切です。
2018/05/15
2020年から大学入試はどう変わるのでしょうか
センター試験は2019年度(2020年1月)が最終となります。現高校1年生から「共通テスト」に移行します
。現在のセンター試験からの大きな変更点は国語数学に記述の問題が導入されます。
また英語では4技能(読む・聞く・書くに加えて話す)を評価の対象にすることが決まっています。
新テストでは「思考力・判断力・表現力」を重視されてきます。
2017年11月に実施された思考調査プレテストでは、複数の情報(文章・図・資料)を組み合わせて思考、判断をさせる問題、選択肢の中には数学では解ナシが選択肢に出ました。
この一部記述は2024年から理科社会への導入も検討されています。
国語は80〜120字程度で答える問題を含む3問程度(古文漢文を除く)出されます。
試験時間は現在の80分から100分に延長されます。
数学は数1の範囲から3問、試験時間は60分から70分へ。記述の評価は3〜5段階の段階別で評価される予定です。
プレテストでは国語の記述が3問出されました。
評価のポイントは文字数の制限を満たしているのか、取り上げるべき内容が含まれているのかの2点でした。
これらのいくつが合致しているのかで段階別に評価が下されました。数学はマーク式の問題の中に3問記述が入りました
。
英語は民間試験活用を基本に評価されます。
グローバル化が進展する世の中での英語のコミュニケーション能力を重視する方向で1日で4技能を評価することが決まりました。
2018年3月には参加要件確認事項が公表され共通テストで活用される7団体24の資格・検定試験が決まりました。
試験参加者は高3以降の4月から12月までの間の2回までの試験結果が活用できます。
活用する資格・検定試験出願時に大学試験センターへの成績を送付することを実施団体に依頼、
その成績を段階別評価が大学入試センターから大学に送付される仕組みになっています。
成績提供システムに参加する資格・検定試験の受検者は、高校3年生以降の4月〜12月の間の2回までの試験結果を活用できます。
活用する資格・検定試験出願時に、大学入試センターへの成績を送付することを実施団体に依頼し、その成績とCEFR(*)に対応した段階別評価が大学入試センターから大学に送付される仕組みとなっています。
但し2023年までは大学入試センターが実施する共通テストでも英語を実施します。
資格、検定試験と共通テストの英語のいずれかか、または双方を活用するかは大学の判断にゆだねられます。
ですから小学校のうちからしっかりと文章を読み込み、まとめる(要約力)をつける必要があります。
2018/04/18
大学入試が難化したというのは本当ですか?
大学入試は難化したことは事実です!文科省の各大学への定員数の指導があり、従来より定員数が厳格に守られるようになったからです。
従来定員の2倍の合格者を出していたところが、昨年は1.3〜1.4ばいになり今年はそれよりもさらに厳しくなりました。
GMARCH以上は1.15倍とも言われています。
予備校の予想が大幅に外れたところもありました。
センター、一般試験ではかなり高得点でも不合格という場合も見られました。
GMARCH以上は二次試験を行いませんから、補欠をかなり出しました。しかし繰り上がりは中々なかったようです。
祝賀会で補欠合格が繰り上がりました。「あ〜よかったと」と思わず声が出ました。
そのあおりを得て日東駒専が上がりました。3月入試もかなりの激戦でした。
本年春の入試では志学ゼミはお陰様で全員合格をいただきました。
よく頑張ってくれました。
倍率がどうであれ目標点に向かって頑張るしかありません!!
2018/03/18
高校入試が終わって少し休みたいと言っています
高校入試が終わって少し休みたいと言っていますが、どうすればよいでしょうか?高校入試、お疲れ様でした。
高校入試が終わって、ホッと一息ですね。
休みたい気が十分に分かります。
高校入時点では同じような学力の生徒が入学してきます。
しかし1学期の中間テストではっきりと上中下に分かれてしまいます。
そこで下位になった生徒は勉強の意欲をなくしてしまいます。
高校は義務教育ではありませんから中学の様には学校も先生も対応してくれません。
ですから赤点を取り続けると進級も危うくなります。
これは昔の小石川に進学した相澤講師氏の実話です。
中学までは1,2番を争う成績でしたが、高校合格とともに塾を離れました。
そして1学期の中間、数学で大きく崩れ、あんなに得意だった数学を投げ出してしまうことになりました。
そして勉強はいいやと言う気持ちになり部活ばかりしていたしそうです。
幸い、小石川は当時、留年はなかったそうですから救われたとよく話しています。
自分の後悔は中3卒業とともに塾をやめたことにあると今でも話しています。
後、高3で戻ってきたときは私立文系になっていました。得意だった英語も基礎からやり直しでした。
一度止めてしまったエンジンは動かすまで、時間がかかります。実際、多くの高校生が高2の冬、高3で戻ってくるケースが多々あります。
遅いと高3の部活が終了してからというケースもあります。
高校入試は通過点(大学入試も通過点)です。
自分の将来なりたいもの、やりたいことに向かって進む通過点です。高校入試で立ち止まっていると遅れが生じます。
中学では塾で「学校は復習」というペースを作ってきたからこそ学校の成績、偏差が取れていたわけですから、それを中断すると大変な状況が生ずることが多いことは事実です。
また高校の勉強は中学と違い科目が増え、進行も早いのです。
多くの諸君が学校で春休みの課題が出されました。それを基に休み明けにテストが行われます。
習っていない所でも宿題として渡される学校もあります。
ですからいかに1学期をうまく乗り切るかが大切なのです。
そうです。
高校は義務教育ではありません。やるものだけが先に進める世界なのです。
2018/02/11
どういう受験生が受かりやすいのでしょうか
受験生各自が試験日、合格発表日を記入した手作りのカレンダーがあります。合格すると○を付けていきます。その度に「やったな。すげえ」などという声が聞こえます。
そうです。志学ゼミでは素直に「人の合格を喜ぶ」ことを大切にしています。
向井講師が今日の合格を発表していきます。
後輩が先輩の合格を喜ぶ同級生が拍手をする。
何かの縁で一緒になった仲間の合格を喜ぶ。いい光景です。
しして受かったら「たまたま得意なところが出ましたから」と謙虚になれる諸君は合格の女神がさらに微笑みます。
そして他人を思いやる心。先日も質問に答えていますと時間がかかってしまいました。その後ろで次の質問を待つ姿がありました。「長くなってごめんね」と言うと「大丈夫だよ」と笑顔で答える。何気ないことですが微笑ましいものです。
こういった何気ない言葉のやり取りが場を和ませ、緊張感も和らぎます。
場はみんなで作るものです。
受験は個人戦のように思われますが、みんなで盛り上がって行くことで勢いが出て来ます。そうして力以上のものも出てくることもあるのです。
受験期は純粋に人の話が聴けるいい時期です。
受験を通して自分を成長できる諸君は合格を手にすることができるのです。
2017/12/29
大学入試はどのくらい受けるのが妥当なのでしょうか
先日、高校の進路相談がありました。10校以上は受けておかないとと言われました。本当にそんなに受けるものなのでしょうか?人によって異なるかと思いますが、私立高校の進路面談では10校は当たり前のように言われるところが多いですね。
もちろんご家庭の事情もあるかと思いますので、センターでいくつ、本入試でいくつとお子様に言われて構わないかと思います。
志学ゼミではセンターで滑り止めを抑えるように指示をしています。まずは受かり癖を付けることが大切です。
ただ一昨年度より私立大学の定員数に対する合格者の割合が厳しくなりましたので合格予想パーセントが上がってきたことは事実です。
日東駒専といわれるランクが軒並みアップしています。
またセンターでは入学手続き日が早い場合が多いですから確認も必要です。
志学ゼミでは入学金の無駄な払いをなるべくしないように事前に計画を立てます。
一般入試でも第一志望が一番は初めに来ないように日程を配置していきます。
志学ゼミでは赤本の出来を見ながら最終調整に入ります。
最後は偏差値ではありません。
もちろん第一志望は別ですが、赤本の出来、自分がその大学の入試傾向にあうかどうかで判断をしていきます。
そして試験日程、合格手続き日をチェックします。そして1人1人表にして保護者様に確認をしていきます。
どこも受からないような進路指導はしていませんのでご安心ください。
学校の進路指導はやはり偏差値で見ていますし手続き日までご覧になられていない場合が多いので参考までにされるのがよろしいかと思います。
2017/11/18
受験生だからと言って特別扱いをする必要はありません
受験生だから勉強だければいいという態度が見られますし、言動にも出ます。どうしたらいいのでしょうか?受験生である前に家族の一員ですから、家族の間で決まったルール、役割を守ることを家族会議で伝えるべきかと思います。
受験生だから特別扱いするのは反対です。
むしろ、掃除や片付けは本人を成長させますのでどんどんしてもらうべきです。
掃除はしていくと「ああ、ここも汚れていた」と気付きます。視野が広がっていくのです。
問題を解く上で、広く物事を考えられるようになります。
受験生にとって必要なことです。
また家族の1員として本人に自覚を持たせるいい機会になるのではないでしょうか。
そして何より感謝の気持ちが出てきます。
先日も受験生に申しあげましたが、「受験をする」のではなく「受験をさせてもらう」ことを意識することを伝えました。
2017/10/10
この時期、受験生の保護者がしなければならないことはなんでしょうか?
子供にとっても親にとっても初めての受験、高校入試になります。何をどうしてやったらいいのか迷ってしまいます。模擬試験の偏差値、合格可能性に一喜一憂しがちですね。お気持ちは非常に分かります。
ましてやはじめてのことですと戸惑うのも無理はありません。
親は受験生のような気持ちになってしまいますよね。
しかし受験をするのはお子さんです。
事細かく聞くとうるさがりますし子供も神経質になってしまいます。
話しかけてきたら話を聞いてあげてください。あまりこれをやったとか、はかどったとかきかなくても子供も子供なりに考えています。
勉強のことはお子さんと塾に任せるしかありません。お母様は健康管理、食事に気を遣い、割り切ることが肝要です。
勉強のことは塾の○○先生と相談して決めて、どうなったかを教えてね。というくらいにしましょう。
学校見学はお済みですか?
もし済まされていない場合は偏差値だけで決めることは危険です。必ず学校訪問をしてお子様に合っているかどうかを保護者の目で見る必要があります。
生徒さんを見てご自分のお子様をオーバーラップしてみてください。「親の目」は当たります。
そうしていくつかの場合を考えて学校訪問をされてください。
できれば通われている生徒さん、保護者様、塾で学校の話を聞かれることをおすすめします。
2017/09/10
どうしてもマイナスに考えてしまいます
よくないことが起こるような予感、感じがすることは確かにありますよね。気持ちが落ち込んでしまうときは特にそうですね。
いきなり「マイナス発言をするな」といっても相手の気持ちは反発を起こしてしまいます。
そんな時は人に話を聞いてもらうことです。
聞く方はただただ聞くだけでいいのです。あれこれとアドバイスする必要はありません。
相手が話をし終わるまで聴ききることをお勧めしています。
話をするとすっきりした気持ちになり、気持ちが切り替わってきます。
またいきなりプラス思考になれと言っても難しいことですから、マイナスの発言が出そうになったらそれを否定して「できる」「できる」と言ってみましょう!
子供さんが苦手科目をするときに問題を見る前から、私は理科が苦手だからとか自分に言い訳を探します。
苦手意識があるとどうしても苦手発言が出がちですが、そこは自分で意識して「苦手発言がでそうだな」注意しようと意識したり、友達同士で「それって苦手発言だからダメだよ」と言い合うのもいいでしょう。
保護者様がお子様のマイナスの発言を聞いたときは、話を聴ききった後に、「できていること」「すぐれているこ」をお子さんに伝えるようにしてみてください。
その際、「塾の○○先生も言ってたよ」など学校や塾の先生の名前を出すのもよろしいかと思います。