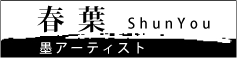塾長の教育相談
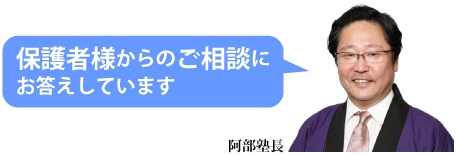
2015/11/26
学校の定期考査の国語を上げるにはどうしたらいいのでしょうか
英語の勉強法と同じようにまずは音読をしてみましょう。英語なら読めない単語や発音が分からない単語、熟語などが出てきますね。その際に出来れば紙の辞書を使ってほしいのです。紙の辞書はその言葉の前後左右に他の語も載っています。自然に目に入りますね。そして大事なところに線を引いてもいいわけです。
それと同じように漢字が読めない、ことばの意味が分からないものが出てきますね。まずはそれをチェックして調べることから始めましょう。
それからもう一度、ことばの意味を確認して音読をしてみましょう。内容がつかめたかどうか確認をしましょう。
何が言いたいのかを考えてみましょう。要約が出来ることがベストですがいきなりは難しいかと思いますので、話を短く相手に伝えるにはどうしたらいいのかを考えてみると良いでしょう。
相手に話すとすると内容が伝わるかどうかを考えることは非常に大切なことです。
これを実際に書いてみて自分で見直すと良いでしょう。
それから問題を解いてみます。そしてどうしてその答えになっていたのかを確認して行きます。
国語は要約力です。つまり言いたいことを掴むということです。これは学年を越えて言えることです。
慣れてくると本を読見終わった後に、筆者の言いたかったことはなんだったのだろかと考えてみることが大切です。
2015/11/08
高校入試のよい受験方法を教えてください
高校入試は通過点と考える。大学入試につながる受験をすることです。都立が第一志望だから併願校を押さえておけばいいというより大学で行かせたい、例えばGMARCH早慶の付属をチャレンジしてみる。そこで受かればそれ以上を目指し、だめなら再度大学で目指す。そうすると高校に入った時、気が緩まずに勉強に目が行きます。
多くの合格した諸君は高校入試で1度勉強モードを解いてしまいます。そうして再度エンジンがかかるのは二年の冬あたりでしょうか。1年から継続している諸君とは基礎力が違いますので当然受験する学校が異なってきます。
志学の現在の塾内模試(センターレベル)のトップは高2生。都立の中上位校です。中学から継続して通塾しています。
彼は自分が体力がないこと、あまり要領がいい方ではないことを知っています。ですから部活はせずにいます。また文系志望だということで英語、国語、社会を勉強しています。特に英語は鉄人に食らいついています。現在190点以上(200点満点)をコンスタントにとるようになりました。
余裕を持って受験することをお勧めしています。
高校は科目が多いので相当要領よく勉強しないと全科目を高得点と言うのは難しいのです。
また同じようなレベルの生徒が集まりますから、ギリギリで合格するとついていくのが大変です。学校の勉強に追いまくられ受験勉強どころではなくなります。ですからある程度余裕が持てる成績の学校に進学することをお勧めしています。
1年時で受験勉強の比率は半々でも2年から受験勉強の比率をあげざるを得ません。3年では9対1以上でが高くなります。
偏差値だけでは決めないこともお勧めしています。
実際に学校を訪問し保護者は生徒の様子を見て自分のこどもを重ねてみる。子供に合っているかどうか親の目に自信を持ってください。行かせたいと思えるかどうかです。また何を優先順位にするか(進学実績、距離、制服の有無、風紀など)
ご家庭でできる1ポイント講座
志学ゼミは(社)スクールコーチング協会の本部としてコーチングを面談に取り入れています。お子さんが話をしたがっている時に話を聴いてあげること。「そうなの。それで」など合いの手を入れてあげることが大切です。子供の話切った感を引き出すことです。
志学は定期テスト対策、内申アップと偏差アップ指導を行っています。
9月から志学では保護者様1人1人と面談を行いました。納得するまで何度でも面談を行います。
受験生の進路相談はもちろんですが、担当講師も生徒、保護者様と面談を行いました。
保護者様には日頃の様子をお伝えしながら進路のお話、出来るようになったこと、課題をお伝えしました。生徒とお面談ではできるようになったことを確認しながら「将来の夢」について話を聞いています。
特に進路面談は春先から繰り返してまいりました。偏差値だけではなく学校を見学した時の保護者様の感想をお聞かせ願いながら繰り返して行なっています。
2015/09/04
高校の志望校の決め方はどうしたらいいのでしょうか
模擬試験の偏差値では判定がでますが、いくつも学校が候補に挙がってきますが実際、志望校はどうやって選べばよいのでしょうか?そうですね。進路の決定はまずはご家庭の方針ということを申し上げています。まずはうちは都立、私立と言う方針を立てるべきかと思います。
その理由を書きだしてみましょう。
その上で学校訪問をしてください。偏差値だけでは決めないでください。学校訪問をして生徒さんの様子を見てください。そのすがたにわが子の姿を重ねてみてください。親の目は正しいものです。あっていないと感じられたら他の学校を考えて行くのがよろしいかと思います。
もちろんお子さんの希望はありますので、何を優先順位にするのかをしっかり話しておくべきです。
大学進学を前提にお考えでしたら、進学実績は大きなウエイトを占めるかと思います。制服の有無、校則が厳しい、そうでない、部活の有無、通学時間等の要因が挙げられます。
また実際に通われている先輩の話を聞いてみるのも良いかと思います。志学ゼミでは高等部がありますので毎年、高校生が中3生に学校の雰囲気、通ってみて良かったこと予想と反していい事、悪い事を話して貰っています。
そうして親子で話う際に子どもの要求を最後まで聴いて、その上でしっかりと話し合いをして決めるべきです。
志学ゼミでは納得するまで何度でも進学相談を行います。実際に学校を訪問して先生方ともお話をしていますので、数字以外のこともお伝えしています。
2015/08/13
小学時代の夏休みに親がしておくことはなんでしょうか
夏休みが続いていますが夏休みの間に親がしておくことは何でしょうかということですね。小学校時代は中学校と違い部活がありません。親子で何かをする良い時ですね。旅行や何かを一緒に作ることも良い思い出になります。
その時、時間が取れるときに子供の話をじっくり聞く時間を設けてはいかがでしょうか。
話を聴くことは「話しを聴くこと」を意識しないとなりません。
何も構えている必要はありませんが、子供が話しかけたときに聴いてやることです。
何気ない話を聞いてもらいたかったということもあるでしょうし将来の話を聞いてやるのもいいでしょう。
話しながらがそうかと思うこともあります。それは大人でも子供でも同じです。また、話を聞いてもらうことは嬉しいことです。
話しながら自分自身で気づきがあるのです。
これは何も小学生に限ったことではありません。中学生、高校生にも言えることです。
どこどこへ行った、何かを一緒に作ったことも大切なことですが、話を聞いてもらいながら何かを気づいたとき子供は成長していきます。
夏は子供は背が伸びるように、成長する時期なのです。
2015/06/19
部活を一生懸命やっているのはいいのですが
「部活でいっしょうけんめいやっているのはいいのだけれどもう少し勉強にも・・・」以前こんな質問がありました。
彼は陸上をやっています。関東大会を目指しています。頭の中は陸上のことでいっぱいで・・・とおっしゃられていました。
「お母さん、関東大会でもすごいのにインターハイですか?それはすごいですね」
先日講師に「イチロー」の話をしたんです。プロフェッショナルで紹介された話でしたが、家にいるときは毎日のようにオフでもカレーライスを食べる。毎日同じ味にできる奥さんを褒めていました。そして自宅から球場に向かう際に顔つきが変わってくる。どうやって集中力を高めるのですか?
「時間」です。と彼は答えます。この時間にはこれをして、あの時間にはあれをしてという風に体がそれを覚えている。それに従っているとのことなのです。そのリズムを非常に大切にしている。つまり食生活も彼にとってはそのリズムの一つなんですね。
遠征先でも食事が終わるとホテルの部屋で足裏マッサージ機で丹念に足裏をマッサージしているのです。地味ですがこれもまたリズムなのです。
まるで「所作」なのですね。書道で硯に時間をかけて墨をすり、筆をならし、版紙に向かう。そういった時間をかけて集中力を高めていく。それと似ています。
さすがに超一流といわれる人は徹しています。しかしながらプレッシャーもある。感じる。そしてそれに立ち向かい「過去のイチローを超える」という話。
実は息子さんもその集中力を高めていくことを、そのすべを知っているのです。すごいのですよ。
「え?」
そうなのです。そうでないと関東大会、インターハイのレベルなんて行きませんもの。すごいんですよ。
「そうですね」
「そうですよ」
「その集中力を勉強にも生かしてくれればいいのですが?」
まずはどうやってその集中力を高めているのかを聴いてみてください。走る前にどうしているのか。そしてどう自分でモチベーションアップしているのか。確かに無意識にやっている場合もあるかとは思います。いやもうそれが体の一部になっているのかもしれませんが。
私もご本人に聴いてみたいですね。彼にはそれができているんですよ。ですから勉強のときも「決めごと」を作っていくのです。
今は確かに大会のことで頭がいっぱいなのでしょう。しかし、それっていい高校生活ですよね。健全な若者の姿がありますよね。進路についてお父様のようになりたいから法学部。陸上の指導者になりたいから体育学部。前向きな悩みですよね。これもまた若者らしい前向きな悩みですよ。
お母さん。もっと親ばかになりましょう。できないことを先に見るよりも自分より優れているところもありますよね。「お母様、高校時代に関東大会に出られたことがございますか?」
「いいえ」
自分より優れているところがありますよ。それを認めていきましょう。部活での集中力があるのですから勉強にも活かせるはずです。また活かせることができるのです。「この子はやればできる」と親御さんが思えばそうなるのです。
内から(家庭)から認めた結果は外からの評価で出てきます。陸上の結果もそれが言えるのではないかと思いますよ。
そういえば例年成績不良者が学期末毎に2泊3日で合宿所によばれるのですですが塾に入ってからか今回はそれがなかったんです。
よかったですね。そうでしょ。形として見えることが多くなりますよ。
みなさん、親ばかでいきましょう。
2015/06/15
子供に言葉が届くためには
小学生の低学年の母親です。子供が何かにつけて「めんどくさい」が口癖になっているのです。親がやはりついていないと勉強をしないのです。「隣にいて」というのです。上や下の子はそうでもないのですが、低学年次に親はどうのようなことを注意して接していけばよろしいでしょうか。「めんどくさい」ですか。ご家庭のテレビないしは外で聞き覚えた言葉なのでしょうね。
以前はやった「微妙」ではありませんが、使いだすと癖になっているのでしょうね。
親が何かをやらそうとすると嫌がるのは子供の常です。自分からやることは親がやるなと言ってもやりますよね。そこに親はジレンマとイライラを感じます。よくわかります。
子供は親の思っているようにはなりません。こうしようああしようと思ってもむつかしいものです。
ではご家庭で「できる」「できる」という言葉を意識して使いお母さま自身の口癖にしたらいかがでしょうか。
また「隣にいてほしい」というのは子供が愛情を求めているときです。そんな時は話を聴いてほしいときですから、とりとめのない話でも聞いてあげることです。
そしてできたことに、単に「うれしい」というのではなく「お母さんはうれしい」と入れると子供の心に響いてきます。
コーチングではI(英語で私)のほめといいます。愛情の愛という言葉もかけています。実践されてみてはいかがでしょうか。
2015/06/03
自信を持ってほしいのですが
小学生の保護者です。何でもいいから思ったことを言い、どんどんやってほしいのですが表に出たがらないというか自信の無いようにも見受けられるのですが。質問にお答えします。
その子、その子の性格があります。表に出たいことそうでない子もいます。親からすると表に出たがらないから、自信のないようにもにも見えるわけですね。
確かに、何事にも自信を持ってやってほしいですよね。自信は自分でつけるもので人が付けてくれるものではありません。
何事においてもすべてに自信を持っている子はいないかと思います。大人でもそうですが不安はつきものです。
もっとこうなってほしい、ああしてほしいというのはあくまで親の欲求です。子供は子供なりに考えて成長しています。
ですからできたことを本人、親も思い出して話をしてみるとよいでしょう。
また、「できなかった話より、できた話をしてやる」「できる」「できる」という声掛けをしてやるといいでしょう。
そうしてやれたこと、できたことを認めてやると「次も頑張る」につながっていきます。
取り組んでみてはいかがでしょうか。
2015/05/17
勉強をしなさいと言わないようにするには
仕事帰りのお父様とお話をさせていただきました。ありがとうございます。お話をうかがいながらなるほどなあと感じることも多々ありました。ありがとうございました。ここ一年「勉強をしなさい」ということがなくなりました。
素晴らしいですね。
自分から進んで勉強する姿を見ることは親にとってうれしいことであり、またそうなって欲しいと思っていました。
実は志学ゼミに来る前、詰め込み式の大手の中学入試の塾に通っていました。家でも私が一緒に勉強を見ていました。子供の表情がどんどん暗くなっていくんですね。
スケジュールに追われ、なんでこうなるのだろうかを考えることが減り、これはこうなるといったパターンを詰め込むことに疑問を感じてはいたものの受験には必要なんだと思い込ませていました。
そんな折、受験のことはさておいて野球をやっているときのようなのびのびとした表情が出ないものだろうかと思ったのです。
そこで受験のことはいったん中断してみようという決断をしました。そしてどうしてこうなるのだろうか?といった素朴な疑問を持てる子供になって欲しいと思ったのです。
お話の中でお子様の良いところをお話をしました。「人といい争わない、人を悪く言わないというところがいいところですね」というお話をしました。お父様はそうなんですね、あの子は・・・とそのお話を受け取られました。
そうなんです。親ばかになりましょう。日本人はどうしても奥ゆかしい人種ですから「いやそうんなことはありません」と謙遜してしまいます。もちろん人様に対して美徳とされることですから大切なことですが。もっと子供に対しては「できる」ことを認めること、それを子供に伝えることが大切かと思います。
あらためて本人の良さを認めてみる。そこでそれを最大に引き出すにはどうしたらいいのかを考えてみる。
お父様、どうして「勉強しなさい」と言わなくともやるようになったのでしょうか?
お父様は塾のおかげとおっしゃいました。もちろんありがたいお言葉ですが、それ以上にお父様がお子様の良さを考え、認めようとしたからではないでしょうか。
つまりご自身の考えが変わった。それにお子様が反応されたのではないでしょうか。
そうなのです。どうしても相手が変わることを誰しも望んでしまいがちなのです。自分が変われば相手も変わる、これはよく言われていることです。なかなかできない私もいます。
テストを見てどうしても×がついたところに目が行きます。どうしてと詰めてしまう。もっとあっている場所、○が付いているところがあるのにそれは見ていないんですね。そこで○がついてあり場所を褒めてみる。そして×がついた場所を本人に説明してもらったらどうでしょうか。
○で認められたお子様は自分から話そうとします。それを聴く。そして「わかってるんじゃない」
つぎは大丈夫だねと言ってあげる。
そうすると知的好奇心もわいてくるのではないでしょうか。
2015/05/08
お母さんが言うからやりたくなくなるって言うんです
お母さんは気になるから言う。子供は言われるとやりたくなくなる。どちらの気持ちもわかります。親としては気になることはその場で解決したいですから当然気付けばすぐしてほしいものですから言いますよね。よく分かります。
子どもは、「言われなかったらやっていたのに、言われたからやりたくなくなった」と言います。
子どもに対して少し言い方を変えてみてはいかがでしょうか。
小さい子なら「○○しなさい」というところを「○○したらお母さんは嬉しいな」というとそうする場合が多かったと思います。
それが大ききなっているんだからして当り前と言う気持ちが強くなってきているのです。そして褒めてやる回数も減ってきているのです。無理に褒める必要はありませんが、やったことを認めてほめることが肝心です。
必ず何か言いたいことの前に、出来ていることを認めて見ることが大切です。例えば「勉強しなさい」といいたい場合、「塾の先生がこの前、考えて解く姿勢が良いと言ってたよ。それを聞いてお母さんは嬉しかった。やればできるからね」と言ってみるといどうでしょうか。
上手く塾の先生等の名前を使うこと。そして自分(お母さん、お父さん)は嬉しかったという言葉を入れることが肝心です。
この「やればできる」という言葉は私もそうでしたが後々自分を支える言葉になってきます。
前向きな言葉は前向きな行動を生み出します。例のように出来ていること(ハードルを下げればいくらでも思いつきます)を投げかけてみると子どもが行動を起こしやすくなります。
やってみてください。
2015/04/20
つい感情的になって怒ってしまいます。
そうですね。親子ですから、感情も出ますね。隣の子だったらそうは言わないところをストレートに感情が出ることもありますね。私も経験してきました。それは良いいことでも悪いことでもあります。皆さんもあまりいい事ではないと分かっていてもついそうなってしまうことはありますものね。
ただ、親子間の感情のぶつかりは後になって子供が大人になった時に分かることが多いとも言えます。真剣に怒ったことは子供の中に残ります。親が真剣に何かを伝えたかったという事実は子供の中に残ります。
「怒る」と「叱る」は別だということを意識しては如何でしょうか。怒りは感情です。叱るは理性です。理屈が付きます。これはこうこう、こうだからこうだよね。とある面諭すことが前提になります。
隣のお子さんにだったらそう言えることがわが子には、「なんで」「どうして」こうできないのと感情が入るのは、親が子にこうなって欲しい、こうしてほしいと言う思いがあるからなのです。
ただ、子どもは親の思ったようにはなかなかなりません。大きくなるにつれてなおさらです。親は徐々に子供から離れ見守る立場にならないとなかなか子供の成長を認められなくなります。
子どもは日々成長しています。反抗期も成長期です。そういったことが言えるようになったんだなあと思うことが子供の成長を認めることになるのです。
ですから無理に思い通りにしようとせず、子どもの話を聞くことから始めてはいかがでしょうか。