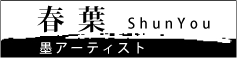塾長の教育相談
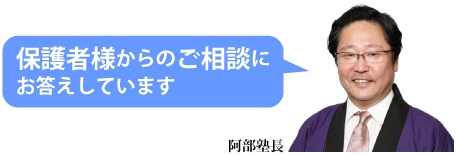
2019/05/03
認めてほめることがなかなかできません
小さい頃は「よくできたね」とほめることができました。大きくなるにつれてなかなかできなくなってきました。
現在、高校生ですが、気が付くと全く褒めちなかったなあと先日塾長とお話をして気が付きました。
「そんなことはできて当たり前だ」とどこかで思っていたようでしたね。
「高校生ほどほめてほしいのではないかと思います」という塾長の話が残りました。
塾長の授業でも出来た事があると、みんなが拍手をして「いいね」とポーズをとるそうです。
なんだかほほえましい気になりました。
「親はどうしてもできていないところに目が行きます」ともいわれました。
「もっとできていることがあるのでそれを認めてほめて行きましょう」と言われて改めてそう思いました。
「内で認められると外でも認められる」そうなのですね。
2019/03/19
大学入試の制度が変わるようですが何を重点に置けばよいのでしょうか
センター試験が来年度で終了し、現高2生から新テストが導入されます。マーク式に加えて記述が課せられます。また英語は業者テストで4技能、読む、書く、聞くに加えて話す試験が加わろうとしています。
まずは記述対策として文章が書けなければなりません。
文をまとめる力です。国語は要約です。
言いたいことをつかみ、まとめることをしていかないと大学の試験では論文形式ですし、実社会に出ると報告書も文章です。
志学ゼミでは小学生時代から文章を書くための主語述語のチェック、話し言葉と書き言葉の違いをチェックしています。
本年度、中3生は毎月1回、「論理de国語」の著者である大沢先生をお招きして作文講座を開設しました。
高校生の英語も要約して言いたいことをつかむ練習をしています。
英語は鉄人の授業では英語で内容を説明をしたり答えたりする時間も設けられています。
とにかく声に出す、手を使うこと。黙読せずに音読することをお伝えしています。
数学は松井講師、中村講師から正しい答案の書き方を伝授されています。
とにかくきちんとした書き方で量をこなすことをモットーにしています。
2019/02/12
合格発表まで落ち着きません。どう過ごしたらいいのでしょうか?」
高校入試、大学入試が佳境に入ってまいりました。落ち着かない日歩が続くかと思います。生徒諸君には「受験ができる」ことへの感謝の気持ちを声に出して保護者様に伝えるように話しています。
一見当たり前のように見えることは当たり前のことではない。誰かが支えてくれるからできている。そのことを思い出すいい機会です。
受験期は純粋に人の話が聞ける良い時期ですから、素直に言葉が入ります。
受験期を通してまた一回り成長していくのです。
そして大事なことは合格発表まで気を抜かないことです。
試験が終わったと安心して遊びたい気持ちもわかりますが、合格発表まで気を抜かないことを常々お伝えしています。
昨年度も滑り止めが補欠合格で本命を残すだけになったSくん。
私の言いつけをしっかり守って発表まで勉強をつづけました。
そして逆転合格を勝ち取りました。
「運」を引き寄せるにはこの「気」を抜かないことが大切だと私は思っています。
1点の中に全国の受験生がひしめいているのです。受験は結果が出るまで分からないのです。
結果が出たらいずれにしろ「受験ができた」ことへの感謝の気持ちが大切なのです。
2019/01/12
入試に際して親がすることはなんでしょうか?
入試間になってきますと落ち着かない日が続くかと思います。お子様が勉強をしていらっしゃる様子を見ながら「大丈夫かな」と思ってくるのもよくわかります。
本人なりによく頑張っています。それを認める。認める言葉をかけてあげることです。
「よくやってるねえ。がんばってるなあ」という優しい言葉をかけてみてください。
家庭も1つの社会です。家庭の中で認められたら外でも認められる結果が出てきます。
そうするとお子様から自然に「ありがとう」という感謝の気持ちが出てきます。
それは「人の合格を喜んでいると自分に回ってきます」とよく話しています。
よい循環を起こすにはよい状況を家庭な内から始めることが大切です。
受験ができる「ありがとう」といことが親子ともども出てきた時がいい受験になってくるのです。
健康管理、食事のことは気にかけていらっしゃるとは思います。
よき応援団として送り出していきましょう!
2018/12/14
合格カレンダーを配布しました
受験生に合格カレンダーを配布しました。受験日、合格日、手続き日を記入できるカレンダーです。
カレンダーを配布する時期になりますとセンター試験がいよいよだなあという感じになり身が引き締まりますね。
私と写真を撮った受験生は全員合格していると向井講師が指摘してから受験生一人一人と写真を撮ることが恒例になってきました。
塾内に写真が貼られていますが、みんなしげしげとみていました。
たまたま私と映っていない受験生が残念な結果になっていたということでしょうが、志学の縁起物になっています。
まあ、受験生の精神安定剤の1つになってくれれば嬉しいです。
驚く受験生をよそに向井講師が次々に写真を撮りました。
そして私から「合格おめでとう」と予祝を行いました。
緊張した受験生の顔が一瞬ほころびました。
さあ、ガンバロー
2018/11/08
「勉強しなさい」と言わない方法はありますか?
「勉強しなさい」は言う方も言われる方もいい気持ちはしません。ストレスもたまりますよね。
特に、親子感は感情が入りますから余計にストレスになりがちです。
今回は2つのご提案を差し上げます。
小さな白版に子供にやらなければならないことを書かせます。
それを家族が見えるところに置きます。
そしてできたら子供がその項目にマグネットのバッチを付けてもらいます。
そうすると子供に達成感が味わえます。
その時必ず認めて褒めると良いでしょう。
2番目は私どものような第3者からお子様に親のかわりに行ってもらうということです。
志学ゼミでは保護者様に「勉強しなさい」と言いたくなったら塾にメール、電話を下さいとお伝えしています。
2018/10/12
スマホばかり見ています。どうしたらいいでしょうか
よく相談に上がる話です。中学高校生のスマフォは今や私たちもそうですが日常の生活に欠かせないものとなっています。
YOU TUBUが出現し、日常茶飯事に見られています。規制もありません。ラインは無料です。そうです、際限がないのです。
それを買え与えたときのルールはどこへやらですね。取り上げると反抗して暴れたという話もよく耳にします。
しかしその都度話し合うべきです。買え与え使用を許したのは親ですから、再度ルールを話し合う必要があります。
感情に任せてやみくもに力ずくで取り上げたり、使用停止の手続きを勝手にとると子供の反抗は強くなるばかりです。
いくら親が料金を払っていると言っても一方的になると子供は耳をふさぎ反抗します。
自分の部屋ないしは勉強するときはスマフォをリビングに置いておくとかのルールは必要です。
確かに街中でスマフォを見ながら歩く大人が横行し社会的なルールを守れない、または当たり前になっている状況で子供たちも育っていますから当然主張もしてくるのも無理のないことです。
また1度使い始めるとその便利さから手放せなくなることも事実ですね。
スマフォを取り上げたら勉強はしない、高校も行かない、塾も行かないと親を困らす話を聞きました。
親のために進学をしてやるといった風にも聞かれる発言に唖然としました。
ですから自らを律することができなければ使用は本来は控えるべきです。
しかしいったん使用を認めたのですから家庭内ルールを決めて守れない場合はルールに従がって対応すべきかと思います。
とにかく話を聴いてそのうえでルールを決めていきましょう。
2018/09/13
自分で計画を立ててできないのですが
計画を立てて実行するのは簡単なようでそうでない場合が多いですね。それは継続することが難しいからです。
また1人で行う場合、意志が必要です。
そこでどうやったらいいのかを再度示しました。
ノートに月の目標を書きます。(教科の指示はこちらでします)
それを週単位でできる範囲を書き込みます。
今月のテスト、目標終了予定を書き込みます。
そして今日やったこと、できたことをノートに記入し提出してもらいます。
それを担当が見てチェックをして声がけをして計画が予定度売りできるようにしていきます。
もちろん事情があってできない場合がありますので、日曜日は調整日としていきます。
また担当がノートを見てスケジュール調整を一緒に考えていきます。
1つできると次もとなります。最初の1歩ができることが大切です。しっかりサポートしてまいります。
ご心配なことがございましたらメール、電話をいただきたいと思います。
2018/08/19
お母さんが言うから勉強したくなくなるといわれました
言わないでおこうと思っていたのですがあまりにもダラダラしていましたので「宿題は終わったの?」と思わず言ってしまいました。「お母さんが言うからやる気がなくなるんだ。今やろうと思っていたんだ」と言い返してきました。
「調子のいいことばかり言って」とあとはいつもの親子喧嘩になりました。
ああ言えばこう言うという年頃だとわかっていてもつい言ってしまいます。
ほおっておくとますますひどくなりそうな気もしてきましたが、第三者から言ってもらうほうがいいのかなあと感じました。
「そうだ、塾にメールして先生から言ってもらおう」と思いました。
親子間はどうしても感情が入ります。感情的になりそうだなと思ったら塾に電話、メールをしてください。
教育相談も随時受けつけております。
2018/07/08
勉強しなさいと言わないようにするにはどうしたらよいでしょうか
勉強しなさいと言わないようにするにはどうしたらよいでしょうか?勉強しなさいと言うほうも言われるほうもいい気持ちはしないものです。
また言ってしまった。また言われてしまった。とお互いストレスが溜まってしまいます。
また反抗期もありますからなかなかお子様が話を聞かないといった話もよく聞く話です。
反抗期は成長期といっても親はなかなかいつも冷静でいられるとは限りませんよね。
親子間はつい感情が入ってしまいます。私も経験があります。
そんな時は第三者から話をしてもらう方がうまくいくときもあります。
第三者から話を聞いたほうが冷静に聞けることもあります。
話を聞いて、お子さんがどうしたいかをまずは聴いてみます。
勉強しなさいと言いたくなったらご連絡ください。
家で勉強をしないようでしたらご連絡ください。
私共がお子様の話を聞いた上でお話をします。
問題をひとりで囲い込まないでご相談ください