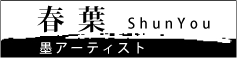塾長の教育相談
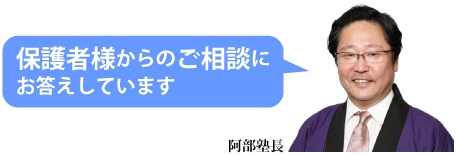
2024/04/18
自信をつけさせてやる気を出してほしいのですが
自信は自分でつけるしかありません。自信を持つには「自分で出来たこと」「できるようになったこと」を体験するしかありません。
そのために私達は必死になってできることを作り上げ「認めて褒める」ことを心掛けています。
自分で「できない」と思い込んでいる場合、いくらそうではないよと言ってもなかなか心が開いてくれません。諦めているときに「あきらめるな」と言っても耳に入りません。
全く反応を示さない場合もあるかと思います。そんな時は、せかさず待つしかありません。
また過去の出来た小さくても成功体験を思い出させてみるのがよいでしょう。どうしてうまくいったのかを本人に思い出すように具体的な事実を伝えていくのが良いかと思われます。
その繰り返しの中で心が開けてきたら、どうしたいかをまずは聴き、何をしなければならないかを本人に確認し、そのためにはどうしたらいいのかを話し合います。
そうして決まったことを声がけを繰り返しながらやるしかありません。
そうして出来たことを「みとめて」「ほめる」。ある場合には認めるハードルを低くする必要が合うかもしれません。
そうして「一つ出来るようになると、また一つと加えていくのです。
その繰り返しの中でご本人が出来ると思えた時が自信につながるのです。
今月の一言 最初からできる子なんていません
2024/04/07
やればできることを味わうために私達が出来ること
今年の新高三の中には英頻を覚えて間違えがゼロになるなど「無理、絶対無理」という発言がよくでていました。鉄人も一生懸命取り組んできましたが、塾でしか勉強をしない皆さんが少なからずいます。
そこでこの春期講習で「やればできる」というものを味わってもらいたく私が一緒になって音読を繰り返し、言えた後、書くということをくりかえしてきました。
イディオム、書き換えを繰り返して声に出して言う。
毎日、毎日、数ページずつ繰り返しました。
毎日、前日までやったものを繰り返しては先に進みました。
高1で英頻の緑が終了しておかなければならないところ、未だ緑が終わっていない諸君にはあきらめの気持ちが見えていました。
そうしてテスト日、それでも予想を上回る3桁に迫る間違えの数。
田端大橋での音読を提案しました。
周りに見られて恥ずかしい。それよりも「悔しい」という言葉が出ました。
ああ、ここから始まるなあと感じました。
明日もやる。受かるまでやる。という言葉を投げかけました。
次の日、そして翌々日。
そうして4日目に全問正解者が2名出ました。
次の日もまた合格者が出ました。
最多の間違えの2名が合格しました。
合格した後自分で自分が信じられないといった表情になりました。
「やればできる」という言葉は経験しないと実感できないものです。
また試験開始時間とい、試験時間をしっかり決めました。
おくれたら試験時間が短くなりますし、やれないかもしれません。
しかし、試験です。入試にはそういった心構えが必要だからです。
毎日毎日、他の業務をせずに試験開始時間に来ては試験監督をしました。
そうして4月6日、全員合格とは言えませんでしたが、不合格者は次はいつやるのかを決めて春期講習を終えました。
「やればできる」「自信は自分でつけるものだ」ということを味わってもらい、やる前から出来ないとはいわないことを各自に身をもって味わってほしかったのです。
さあ、これから。
今月は英頻を1冊、ミス1桁で通すぞ!
2024/03/10
次につながる受験とはなんでしょうか
受験が次の受験につながるようにしてほしいのですがそれには受験の仕方が重要です。高校入試を例にとります。
大学進学が前提とします。
都立、私立高校が第一志望で、皆さんの多くは併願を決めて受験をされます。そして第一志望に合格をすると安堵します。それはそれでいいのですが、そこで更なる高みを見据えてチャレンジする受験をしてほしいのです。
例えば行きたい大学の付属高校を狙ってもいいのではないかと思います。
いつもどこかでチャレンジをする姿勢が大切です。そういった受験をしてほしいのです。
以前、都立高校の発表の日、日比谷高校の受験を失敗した足で志学ゼミに来られた親子がいらっしゃいました。
彼は3.11の東日本大震災の中、国境なき医師団を見ました。
自分もそういった医師になりたい。そう思ったのです。
国立をはじめ、都立も合格できると言われていたそうでしたが、残念な結果に終わりました。
そうしてその日から医学部受験に向けてスタートを切ったのです。
そうして野球部と両立させながら、3年後、国立大学の医学部に進学をし、在学中にアフリカの無医村の村にボランティア医師として勤務をしました。
現在、大学で研究医をしながらアフリカの無医村の村を回っています。
人生には失敗はつきものですが、うまく行かなかったことを経験していると、悔しさとともに次はどうすべきかをいち早く考えるようになります。
「満足したら伸びは止まる」
私、自身に言い聞かせている言葉でもあります。
今月の一言 高みを見続ける受験は次につながる!
2024/02/18
入試を終えたら何をさせたらいいのでしょうか
ズバリ予習です!中学、高校入試を終えた皆さんは中学の予習、特に英語の教科書の予習、数学の予習は必須ですね。
私立は公立よりも進行が速いですから、中1の段階で中2の内容に入るところがほとんどです。
1度わからなくなると取り返すまでに時間がかかります。
「学校は復習」のペースを崩さないことです。
志学ゼミでは中学入試の皆さんも中学予習コースに切り替えています。
大急ぎで1学期分の予習(中2の連立方程式まで、英語は1学期分の教科書の内容)を行います。もちろん、シラバスを見て確認をしてまいります。
高校入試は2月で終了いたします。3
3月からは高校の内容にどんどん入ってまいります。
ここで終了される皆さん、都立第一志望の皆さんは貯金がなくなりますので要注意です。
また、中高一貫の学校に比べて1年遅れていますので、肝に銘じて高校に進学をしてください。
大学入試の皆さん、大学入学後にすぐTOEICの試験が行われるところがほとんどです。
社会人になるまでに730点をクリアすることが目標です。
また大学に入るまでに世界史以外の選択者は世界史の勉強をしておかないと大学の講義がよく理解できないこともあります。
またこの機会に名著名作を読むことも勧めています。
今月の一言
入試は人生の通過点、なりたいことへの通過点です。
2024/01/18
合格するご家庭はここが違う
長年塾をやっておりますと、受かるご家庭とそうでないご家庭の特徴が見えてきます。ご家庭内のコミュニケーションが取れ、親子間関係が良好なところは合格する場合が多いですね。
逆の場合、特に親に反発をして意見を聴こうとしないご家庭は自分勝手な受験に走りがちですから要注意です。
親は子供に意見を押し付けようとせず、子供の話を聴こうとすることが大切です。
いきなりうまいコミュニケーションをとることは難しいとしたら、話をしたがっている素振りが出た時は黙って聴くことでをお勧めしています。
家庭も1つの社会です。親は子供の後ろ盾です。親が子供を認めると、外で認められる循環が起こります。
受かる子の多くは謙虚で感謝の言葉口にするようになります。
志学ゼミでは受験が出来ることへの感謝の言葉を述べることを生徒に勧めています。
朝起きて、体が動く「ありがとう」
保護者様のお陰で試験が受けられる「ありがとう」
試験会場に無事着いて試験が受けられる「ありがとう」
試験が無事受けられた「ありがとう」
試験が無事終了した「ありがとう」
今月の一言 受験が出来る。ありがとう。
2023/12/19
受験期に保護者がすること
受験生の保護者が出来ることは何でしょうか?受験が近ずいてきますと、緊張感も増してきますね。
年が明けるといよいよだなという感じになりますね。
通常通りにしていろと言われてもなかなか難しいですね。
私たちを含めてみんな応援団です。
保護者様は健康管理、塾は勉強管理と分けて考えてくだい。
『よくやってる』と思えなくとも本人なりに頑張っています。
家庭で認められたことは外でも認められていきます。
良い循環を起こすには「認めて褒める」ことです。
具体的に認めて褒めるところがないと思われる場合は、子供が生まれてきたときのことを思い出してください。
「今日も元気に生きている」ありがとう。
出来ることが増えると、次も次もとなってまいります。
そうです。限がなくなります。
本人なりに頑張っている。
私は塾生に「受かろうとせず、今持っている力が出し切れる受験であればいい」
「縁があるところに行くことになっている」という話を伝えています。
今日の一言:「大丈夫」を合言葉にしてみましょう
2023/11/22
親子間の関係がうまく行っていると受験はうまく行く場合が多い
子供の話をしっかり聴ける環境にあると子供は親に話をしやすいと言えます。何でも話し合える環境とは言いませんが、相談ができる環境は必要かと思います。
何か話を聴いてほしい素振りや、悩んでいる様子が見られたら話を聴いてあげる必要があります。
そこで無理に解決をしようと考えないことです。
解決できなくても話を聴いてもらえるだけでもすっきりすることはあるかと思います。
無理やりの解決策は子供に意見を押し付けることにもなりますのでご注意ください。
子供の話を聴くことだけを念頭にして聴くスイッチを入れてください。
そして話を終えるまで聴ききることです。
子供の言い分を認めて「そうか、そうか」と聴いてやることが大切なのです。
途中で言いたいことが分かっても遮らないことです。
他愛のない話になってもいいのです。
子供は訊いてもらったという安心感を持てるのです。
それがいい親子関係の第一歩です。
話がしやすい環境作りが親子関係がうまく行く環境作りと言えます。
いざというときのよりどころは両親です。
家庭内で認められた子は外でも認められます。
ですから受験がうまく行きやすいのです。
2023/10/11
10月は焦っていいのです
10月になって少し焦りが見え始めたようですが大丈夫でしょうか?勉強が本腰を入れ始めるとやらなければならないことがたくさん浮かび上がります。
これも、あれもといった感じでしょうか。
勉強を始めた証拠です。
勉強をすればするほどやらなければならないことに気が付きます。
まずはやらなければならないことを書き出してみましょう。
そして、優先順位を決めます。
そして1日の無理のないペースを決め終了期日を決めます。
ひとりで決められないときは講師と相談しながら決めてもいいのです。
例えば日本史、世界史。これまでやったことに文化史が加わります。現役生の苦手なところです。
それをしっかりこなして頭に入れて入試問題に進むのです。
やみくもに赤本(過去問)を解いて出来を見ても地に足がつかないものとなり、かえって焦ってしまいます。
11月に焦りだすと後がない分、余計焦ります。
そのために10月の計画が特に大切なのです。
今月の一言 ひとりで焦らず相談してください!
2023/09/17
子供を励ますにはどうしたらいいのでしょうか
受験生を励ます。子供に気持ちが伝わるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
子供が出来た事を褒めることが大切です。
その際のポイントをお伝えします。
ただ褒めるだけではなく、具体的に出来たことを挙げ、また出来ていることを挙げて認めてください。
その際に私達の名前を利用してかまいません。
「○○先生はこう言ってたよ」と言ってみてください。
そしてここが肝心です。
「それを訊いてお母さんは又はお父さんはとても嬉しかった」と言ってみてください。
コーチングで言うI(私)の褒めです。
単にほめるよりもこの言葉を添えると心に響きます。
誰かに褒められたことをお母さん、お父さんが認めてくれたということになりますから嬉しさがまします。
そしてまた頑張ろうとなるわけです。
失敗したこと、叱られたことは残りますが、ほめられたことは意外にそうは残りませんから、継続することが肝心です。
お試しください。
今月の一言:認めてほめる、その繰り返しの中で子供は伸びていきます
2023/07/11
「もう少しこうなってほしい」と思ってしまうのですが。
もう少し何とかならないのかな」という親としての気持ちはよくわかります。子供に対しての期待はどうしても生じます。
私にも経験がありますからよくわかります。
私もそうでした。しかし子供の一人が交通事故に遭い、生死をさまようことがありました。
そうなると「生きていてくれ」と思うのです。奇跡的に助かったその子を見ながら「今日も生きていてくれてありがとう」と思えるようになりました。
生まれてきたときのことを思い出してください。「嬉しかったですよね」
まずは「今日も元気で生きていてくれてありがとう」というところからスタートしてみましょう。
そうして子供の存在を受け入れると、この子なりないやっているんだ「よくやっているね」という言葉をかけて見ましょう。
そして子供に「次はどうしたい、どうなりたい」ということを訊いてみてください。
それをじっと口を挟まずに聞いて見てください。
そうして子供が話し終えるまで待ってあげてください。
そして「いいね」と声をかけてあげましょう。
今月の一言 「認めてほめる」ことを意識してみませんか。